マラソンの練習方法についてインターネット、本、あるいはSNSなどで調べているとき、LSD・ジョギング・ランニングという言葉の使い分けが気になったことありませんか?
もしくは、会話の中でLSD・ジョギング・ランニングという言葉をどう使い分けたらいいのか疑問に思ったことはありませんか?
このテーマについて書かれた記事は世の中に多くありますが、どうやら世界共通の明確な定義はないようで、記事によって諸説あります。

この記事では、3つの言葉の違いについて説明するだけでなく、練習計画を立てる際にどのように使い分けると良いかお話します。
- LSD・ジョギング・ランニングの違いについて知れる。
- 練習計画の立案においてLSD・ジョギング・ランニングをどう使い分けるのか知れるので、練習の成果が出やすくなる。

LSD・ジョギング・ランニングをどう定義するか

スピードが速い順に並べると「ランニング→ジョギング→LSD」ということになります。
これは異なる意見を見たことがありません。
ですがLSD・ジョギング・ランニングについて明確に速度で定義づけることは困難です。同じ速度でも、その人の走力によって負荷や感じ方は全く異なるからです。
これら3つは「自覚症状」と「練習目的」で使い分けることを私はお勧めします。
ジョギング

まずはジョギングを基準に考えると、LSD・ジョギング・ランニングを整理しやすいと思います。
ジョギングとは、ゆっくりと走ることです。
速度で定義してしまうと、息切れしてしまう人もいると思いますので、自覚症状でジョギングを定義しましょう。
「長く走っても息があがらない」「胸部に負担を感じない」「走りながら会話ができる」このような状態がジョギングと言えます。
心臓や肺への負担が少なめなので、長く走ることができます。
いわゆる有酸素運動になります。
長時間継続する有酸素運動を行うことで有酸素でのエネルギー供給(ATP再合成)能力が向上します。これにより全身持久力が向上し、以前よりも高い負荷でも運動を長時間行えるようになります。
- 長く走っても息があがらない
- 胸部に負担を感じない
- 走りながら会話ができる
LSD(Long Slow Distance)

LSDとは長い距離をゆっくり走ることです。
「ゆっくりと走る」というとジョギングと一緒になってしまいますが、ジョギングよりもさらにゆっくり走り、「ジョギングよりも長い時間を走る」ことが目的の練習です。
「1km7~8分ほどのペース」と書かれていることが多いのですが、数値はこだわらなくて良いです。
よく言われる「1km7~8分ほどのペース」では長く走れない人も当然います。
自分自身が無理なく長く走れるペースまで速度を落としましょう。
LSDでは走る「距離」を決めるのではなく、走る「時間」を決めて走ることが推奨されています。
距離を決めるとペースが速くなりがちで、長時間走るという目的が達成できないからです。
LSDでは60分など長い時間を走りますが、いきなり長い時間を走ると故障するので、トレーニング慣れしていない方は10分程度から始めて少しずつ延ばしましょう。
慣れてきたら120分、180分と走ることも有効です。
LSDも有酸素運動なので、有酸素でのエネルギー供給能力が向上する点はジョギングと同じです。
ただし、「高負荷であるほど生理学的な効果は高い」というのが基本ですので、同じ時間練習するのであればジョギングに効果で負けます。
スピードが控えめなので、正しいフォームを意識することが大事という意見があります。
一方で、実際のレースよりスピードが遅すぎるため、走りが小さくなってフォームが崩れやすいという意見もあります。
私は、「スピードが違いすぎるので、レースと同じフォームで走れるわけがない」と考えています。
手足の動きが小さくなるのは仕方ありませんが、体幹を安定させる意識をすることは大事です。
背中を丸めたりせずに背筋を伸ばして、地面からの反発力を前方への推進力に変える意識をもちましょう。
- ジョギングよりもゆっくり走る
- ジョギングよりも長い時間走る
- 走る距離ではなく「時間」を決めて走る
ランニング

ランニングはジョギングよりも速く走ることです。
目標の距離とタイムを設定して走ることが多いです。
ペース走、レペティション、ビルドアップ走、インターバルなどがランニングに該当します。
スピードと距離は種目によって異なりますので、種目によっては「息があがる」「胸部に負担を感じる」「会話ができない」など自覚症状も様々で、有酸素運動ではない状況もみられます。
ペース走は「1km4分」などの設定で、5km、10kmなど距離を決めて走ります。
レペティションは「1km全力×5本(休憩15分)」のような走り方です。
これらのランニングで得られる効果はそれぞれ異なりますので、それぞれの解説ページをご覧ください。
自分が何の能力を成長させたいのかを考え、それに応じたランニングを選ぶことになります。
- ジョギングよりも速く走ること
- 目標距離とタイムを設定して走ることが多い
- ペース走、レペティション、ビルドアップ走、インターバルなど種類が多い
LSD・ジョギング・ランニングをどう使い分けるか
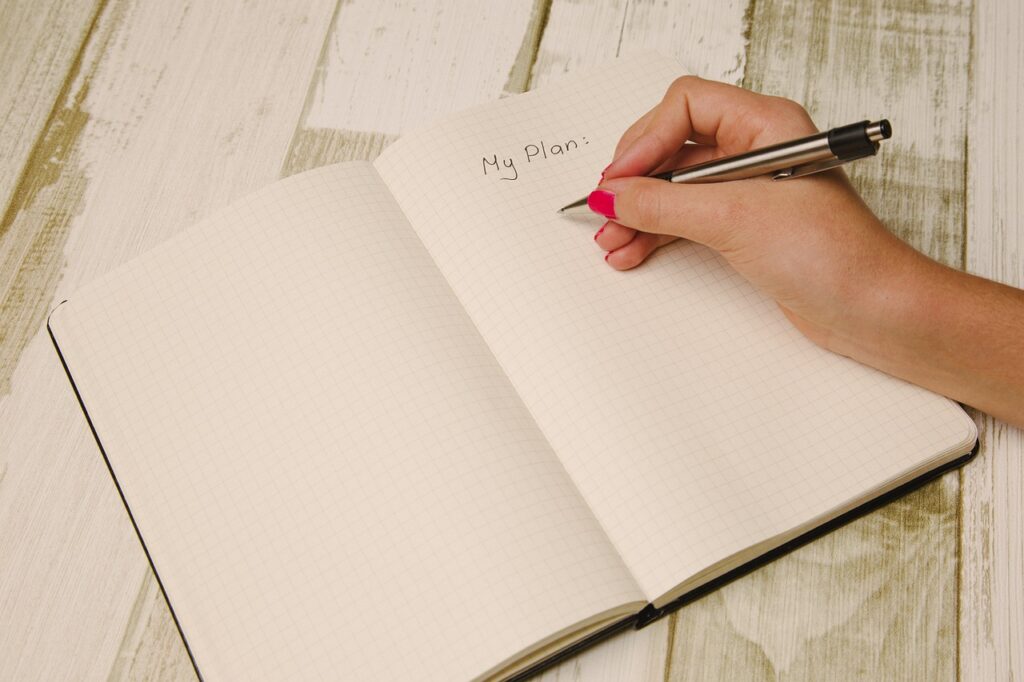
言葉の違いだけを知るだけではなく、どう練習計画に役立てるかもお話します。
まだフルマラソンを完走したことがない人
初めてフルマラソンを完走しようというのであれば、ほとんどの人は4~6時間ほど走り続けなければならないことになります。LSDという意識で、ゆっくりでもいいので長い時間走ることが効果的です。スピードを落とすことで、長時間走り続けることに体を順応させます。いきなり長い時間を走ると関節を痛めたりケガをしますので、慎重に時間を延長しましょう。
フルマラソンを完走はしたけれど、途中で歩いてしまった人
途中で歩いてしまう理由は様々ですが、長時間走り続けることにまだまだ慣れていない可能性は高いです。LSDで長時間走るということが効果的です。3時間過ぎたころに歩いてしまった人は、3時間以上を走れることを目指しましょう。ただし、長時間の運動は関節を痛める可能性も高いですので、無理はせずに慎重に時間を伸ばしましょう。
目標タイムがあるのであれば、LSDだけでなく、目標のペース、あるいは目標以上のペースで走ることも必要です。ペースの設定をしたジョギング・ランニングも行いましょう。
フルマラソンを歩かずに完走できる人
LSDでの練習は走力向上にはあまり効果的ではありません。例えば、フルマラソンを5時間で完走できる人が3時間のLSDをしても、まず時間が短いですし、3時間で走れる距離はフルマラソンよりも短いですし、そのペースもフルマラソンを走るときより遅いものになります。時間、距離、スピードいずれも自分の能力より低い練習になってしまいます。
LSDは有酸素運動ではあるので有酸素運動能力の向上は期待できますが、「高負荷であるほどトレーニング効果は高い」というのが基本ですので、低負荷の運動は費やした時間に対して成長効率が悪くなります。
ただし、走力向上ではなく、走力の維持、疲労抜きの練習としてはLSDも良いでしょう。
走力向上を目指すのであれば、LSDではなくジョギングやランニングという認識で目標ペースと同等、あるいはそれ以上に速いペースで走る練習を取り入れましょう。
まとめ
LSD・ジョギング・ランニングの3つを分類すると以下のようになります。
- LSD:長時間走るために、ジョギングよりもスピードを落として走る練習(有酸素運動)
- ジョギング:ゆっくりのスピードで長距離走ること(有酸素運動)
- ランニング:目標の距離やタイムを設定して走ること。ペース走、レペティション、インターバルなど、目的によっていろいろな種類がある。(有酸素~無酸素運動)
LSD・ジョギング・ランニングのいずれかで練習するかは、今の自分の状況や目的に合わせて選択します。
低負荷でもいいので長時間に慣れたいのであれば、LSDを選択しましょう。
既にフルマラソンを歩かずに完走できる人が走力を向上させたい場合は、ジョギングやランニングである程度のスピードを出しつつ練習しましょう。
目標達成に向けて、いい練習計画を立ててください!

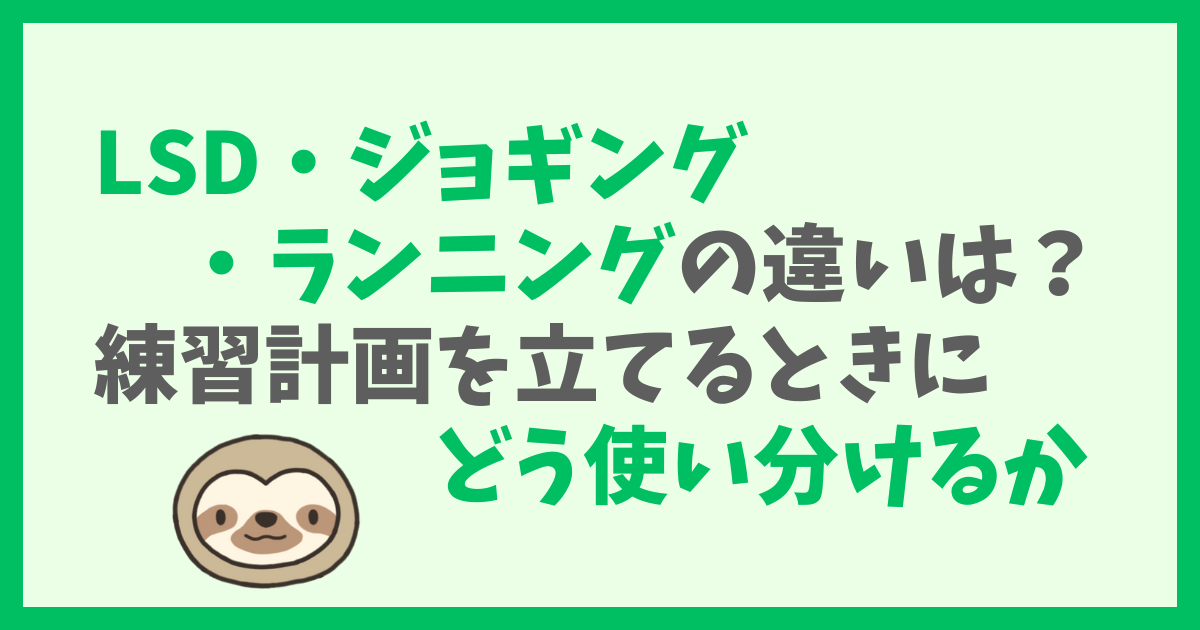
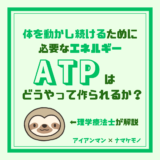
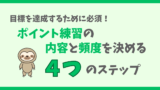
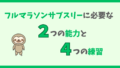
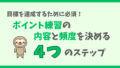
コメント